今回は実際に受託系IT企業に転職した「しう」が模擬プロジェクトで、どのような学びをおこなっているのか記載しています。
9月で実際の開発現場に入る前の最後の研修期間になるので、気合いを入れて取り組みました。
 しう
しう特に転職ドラフトは人気サイトやから、他の人には内緒やで!
記事の信頼性:未経験からIT企業の開発の仕事へ転職に成功した「しう」が書いています。模擬プロジェクトでの学びを日記代わりにつけています。
模擬プロジェクト3【設計書通りの実装】


模擬プロジェクト3では用意された設計書通りに実装をしていきます。
今まで取り組んできた模擬プロジェクトでは、設計書も修正してから実装をしていました。
今回の模擬プロジェクト3では設計書の修正作業が減る分負担は減りますが、指示されてない方法で実装できない苦しさもありました。
また、模擬プロジェクト3では、JSON形式で受け取ったデータをXML形式に変換して扱いました。
初めにJSON形式でAのサーバーに送り、AからXMLに変換してBのサーバーにデータを送ります。
そのため、Advanced Rest client というアプリを利用してJSON形式でAのサーバーに送るなど作業を模擬プロジェクト3でおこないました。
データの形式の違いは独学時にはあまり意識していなかったですが、今回の模擬プロジェクトを通じて有意義な学びを得ることができました。
模擬プロジェクト4【判定機能の追加】
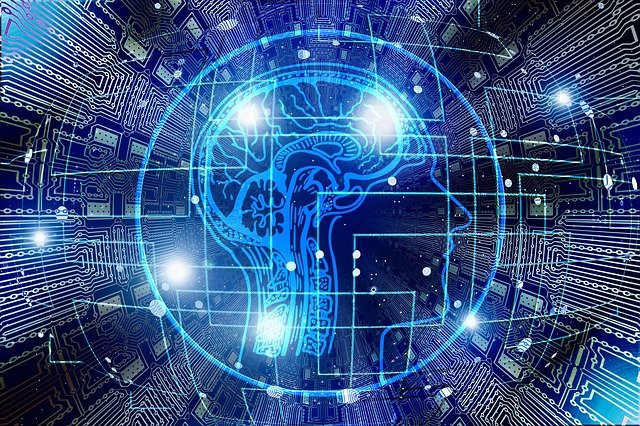
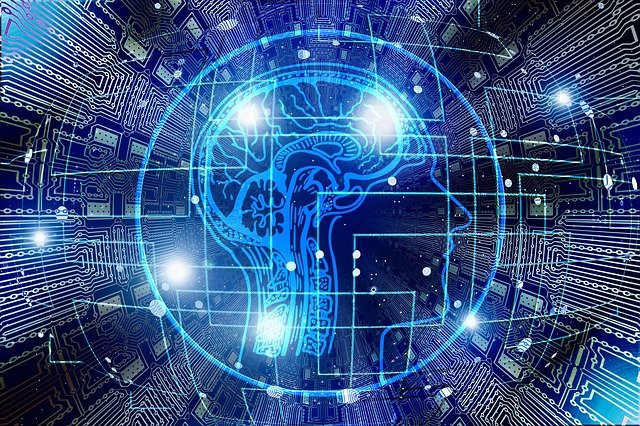
模擬プロジェクト4では、受け取ったデータが条件に該当するかの判定機能を追加する改修をおこないました。
例えば、Aさんの生年月日のデータ(1990年1月1日生まれ)を受け取ったとします。
そのデータから2021年1月時点では31歳ということを判断して、レスポンス時にその情報を追加するイメージです。
今紹介した誕生日を判定する例であれば作業は簡単です。
しかし、年齢がBさんより上か、大阪府の平均年齢より低いかなど判断する場合は複雑になります。比較をする場合に比較対象に関するデータをDBから取得する必要があるからです。
この判定をする時に、データベースからデータを取得する回数をどれだけ少なくできるかが大切です。
一度データベースで取得したものを利用する場合は、2回目以降データベースに接続して取得せずに「一回目で取得したデータを使いまわす」ことが大切です。
特に実務経験が少ない時はしてしまいがちな部分なので意識をして処理時間を増してしまわないように気をつけましょう。
発表会【模擬プロジェクトの集大成】


9月の最後には模擬プロジェクトで学んだことの発表会があります。
パワーポイントに発表内容をまとめて、模擬プロジェクトではどのような作業から何を学んだか、今後何を目標に努力をするのか発表します。
この発表ではとても緊張しましたが、練習通りに上手く伝えられました。
IT業界で働く上で上流工程を担当する場合はお客さんとやり取りをする機会も出てくるので、その時に備えた練習になったと思います。
まとめ
いかがでしたか?
次の順番で模擬プロジェクトで体験した内容について紹介しました。
- 模擬プロジェクト3【設計書通りの実装】
- 模擬プロジェクト4【判定機能の追加】
- 発表会【模擬プロジェクトの集大成】
ぜひ参考にしてくださいね。
ちなみに、「しう」の配属先は希望をしていた某アプリの開発の現場になりました。
実装などの開発経験を積むことができる部署で働くことができそうので嬉しいですね。
10月から現場に配属になりますが、今後も技術力の向上に努めていきたいと思います。
☟あわせて読みたい 「しう」のオススメブログ
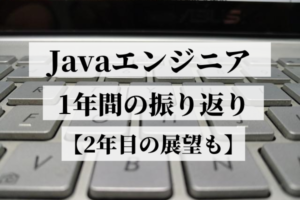
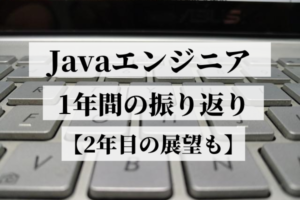
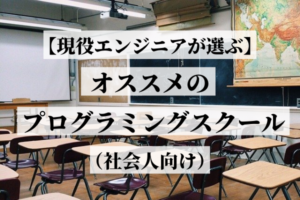
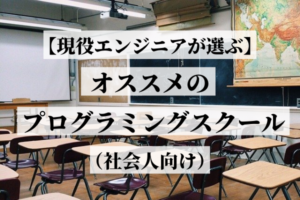



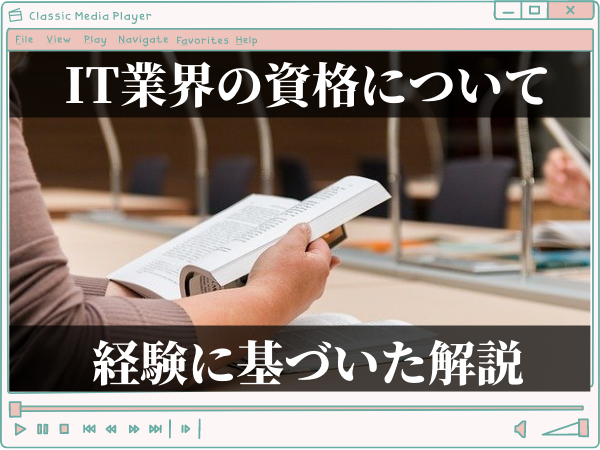
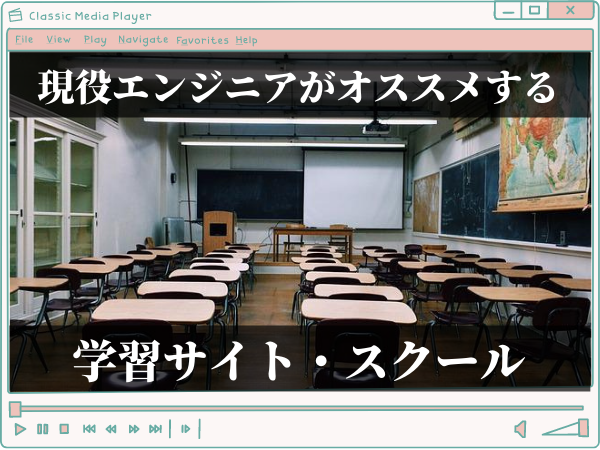
の-1.png)
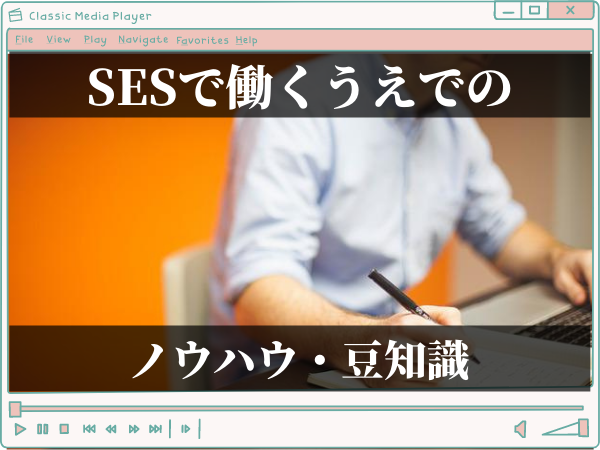



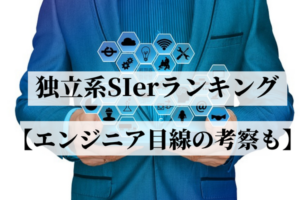

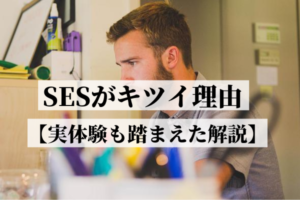
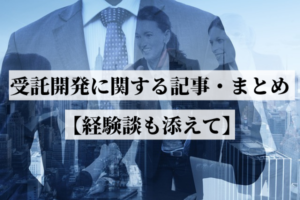
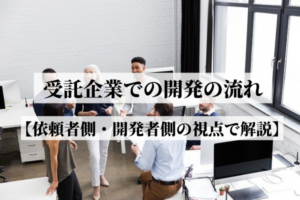
コメント