毎日忙しい日常を送っているとなぜ、こんな勘違いをしてしまうのかということがありますよね?
そんな人は「無知の科学」を読むことで、人はなぜ錯覚をしてしまうのかを学ぶことができます。では、今回は「無知の科学」をご紹介していきます。
記事の信頼性:月に6冊本を読む「しう」が見つけたオススメの本を紹介しています。
これぞと思った本しか紹介にしていないので、ぜひ一度読んでみてください。
1~4章【なぜ間違った考えを抱くのか】

序章
1~4章では勘違いや錯覚をしてしまうのかについて触れています。その理由として人は無知である。つまり、普段使っているトイレがどのような仕組みで動いているかすら説明できないと言っています。
同じコミュニティーにいて、他の人が知っていることを、あたかも自分が知っているようにふるまうのが人間だそうです。
決して、悪いことばかりではないけれど、自分の理解度を過大評価してしまうバグが人の脳にはあると説いています。
「知っているのウソ」
優秀な専門家ですら、些細なミスを犯します。その例として、核爆弾に使われる放射性物質の一つである、プルトニウムの性質を調べていた物理学者の例を挙げています。
2つの半球の形をしたベリリウムとその間にあるプルトニウムの距離を保つためにマイナスドライバーを間に挟んでいて、事故を起こしたことは笑い話のようです。
しかし、実際に1950年代にあったことです。
この章の最後には人は錯覚の中で生きていると書かれています。
世の中の仕組みを理解していると思い込むことで、世界の複雑さを無視して生きている人が多いのだそうです。
なぜ思考するのか
この章ではすべての出来事を記憶することができる人(超記憶症候群)の話が出てきます。
しかし、その能力を持っているせいで、人の優れた能力である抽象化する力を活かすことができないとも言っています。
違う犬種の犬が3匹いた時に、超記憶症候群の人は3匹が違う犬種であっても、なぜ犬とひとくくりにしているか理解できないのです。
つまり、細かい部分に目が行き過ぎてカテゴリーわけが下手になってしまうわけです。
どう思考するのか
ここではパブロフの犬の例から、動物は因果関係を学べると伝えています。(因果的推論能力)
そして、人間は特に因果的推論の才能にめぐまれています。だからこそ、なぜそうなるのか考え、その力を伸ばすことが教育でも大切なのです。
ちなみに、原因から結果を推測できる動物は多いが、本当の意味で結果から原因を推測できるのは人間だけだとも書いています。
また、この能力を活用することで、物語や小説からも人は学びつづけるようになりました。
なぜ間違った考えを抱くのか
人が間違った考えを抱く理由として、目の前でおこっている原因を間違ったところに求めてしまうからだと書かれています。
例えば、蛇口をひねると水がたくさん出る。アクセルを踏めば、車は加速する。だから、年齢を重ねるほど、睡眠時間は増えるというようなものです。
上の例では、ある場面で比例の関係があるからと言って、反比例の関係にも関わらず、比例の関係を当てはめてしまうことが原因です。
このように理解が浅いことに対して、深く考えずに判断することは危険です。
5~9章【体や他者を使って考える】

体と世界を使って考える
人は自分のいる場所についてよくわかっている気分になりがちです。しかし、部屋の全体像を思い浮かべようとしたときに、意外と思い出せないものです。
つまり、この理解しているという実感自体がまやかしなのです。
しかし、すべてを脳で処理しようとしないことメリットもあります。
机の上の書類やカレンダーを見ることで何をするべきか思い出すことができます。
要するに人の脳は外部とつながっているのです。
そして、その外部には他の人やテクノロジーも含まれています
テクノロジーを使って考える
人間は技術的変化を受け入れるようにできています。人間の脳や体は新しい道具をまるで体の一部であるかのように取り入れるようにできています。
しかし、ここ数年で変わったこととして、技術がもはやユーザーがコントロールできる単なる道具ではなくなったことです。
また、人間は知らなかった情報を、インターネットを検索してその情報を見つけた後、記憶違いをして「もともと知っていた」と回答するケースが多いことにも留意が必要です。
では、コンピューターと人間の違いは何なのか?それは、(今はまだ)志向性を共有しないというところにあります。
人間同士であれば、早く到着したくない時に遠回りで行く方法を考えられるが、カーナビなどは最短距離しか示すことができません。
人は他の人と協力することで目的を達成してきました。狩猟採集時代には、連携をすることで自分より大きい動物を捕らえて食べることもしてきました。
そのような志向性の共有を、コンピューターとはできないと書かれています。
10年後、20年後には今と同じ状況になのか、予測はすることはできませせんが。。。
10~12章+結び【賢さの定義とは】
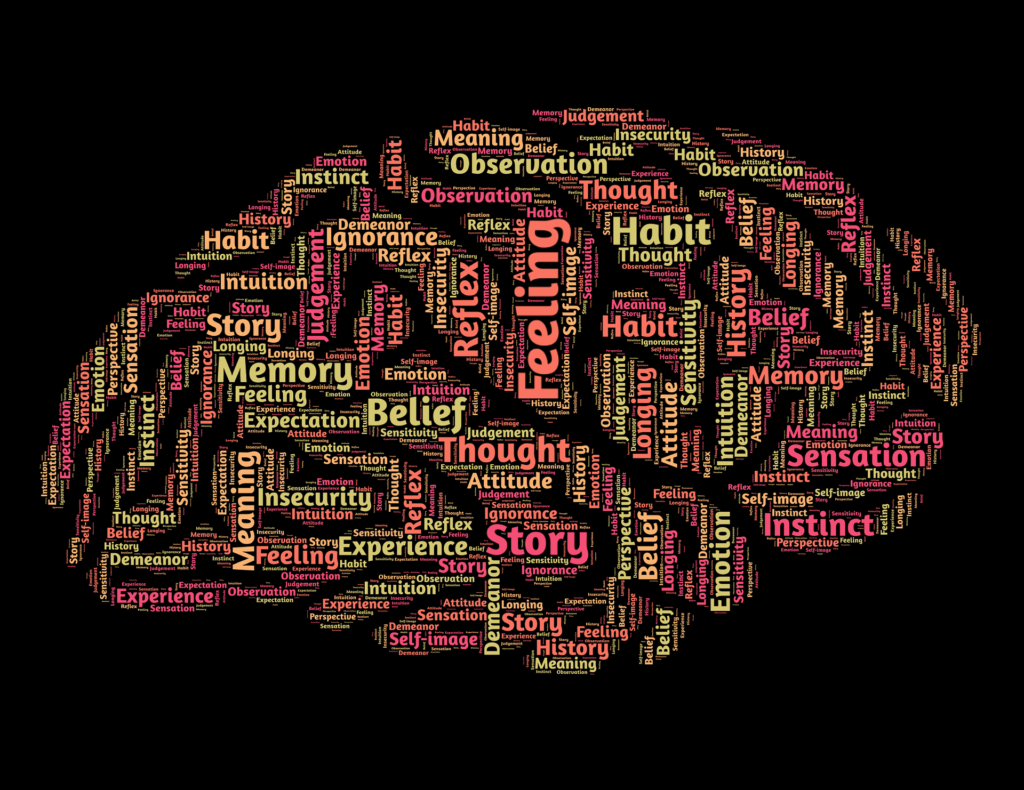
賢さの定義とは?
賢さの定義について今までは、1人の人間についてのIQなどが話題に上がることが多かったです。しかし、本書ではそれで人間の賢さが測れるのかと問いかけています。
人間を人間たらしめるのは、他の人と連携をして、目標を達成することだと先ほど述べました。
だとすると、1人の人間の知能指数だけでなく、集団で目標を達成する力を測る方がよい有意義ではないかということです。
そのためには、情報量を増やすだけではダメで、意思決定のルール作りや、ジャスト・イン・タイム教育(必要になったときに必要な情報が届くようにすること)、自分の理解度を確認することが有効だとしています。
自分の知らないこと情報を、どのように取得するか、その方法を身についけることが大切だと説いています。
結び
本書の最後では、錯覚は必ずしも悪いものではないとも書かれています。合理的な判断で自分のできないことを正確に判断できるL、すべてを理解しようとして、自分は物知りだと思っているSの2人がいるとします。
この2人ではLの方が冷静な判断ができるかもしれないが、Sの場合多少不可能だと思うことでも挑戦して取り組むことができます。
どちらかが良いという話ではなく、どちらにもメリットとデメリットがあり、うまく付き合うことが必要なのです。
つまり、正確に物事を把握する力と多少錯覚を抱いてでも夢を持って挑戦する力の両方が人間には必要だということです。
いかがでしたか。今回は「無知の科学」についてご紹介しました。ぜひ、一読することで人間の脳の性質を学んでみてくださいね。

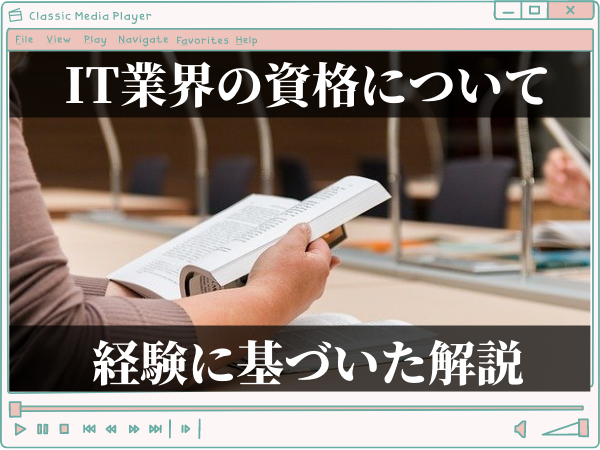
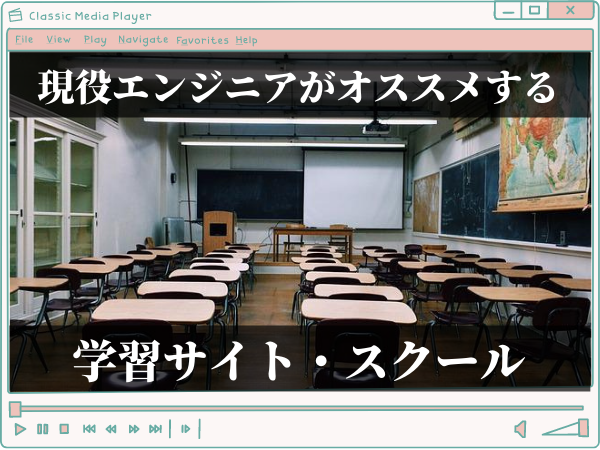
の-1.png)
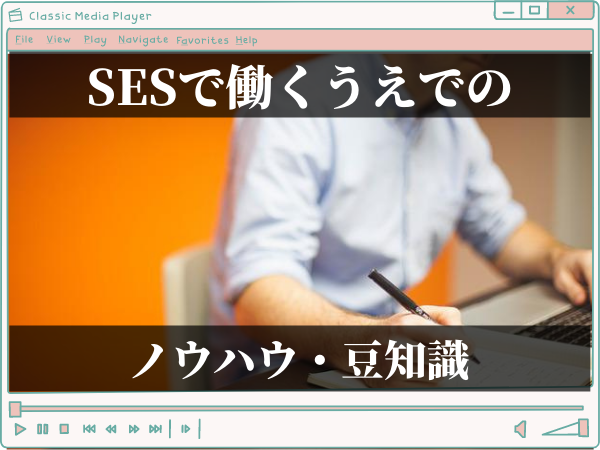
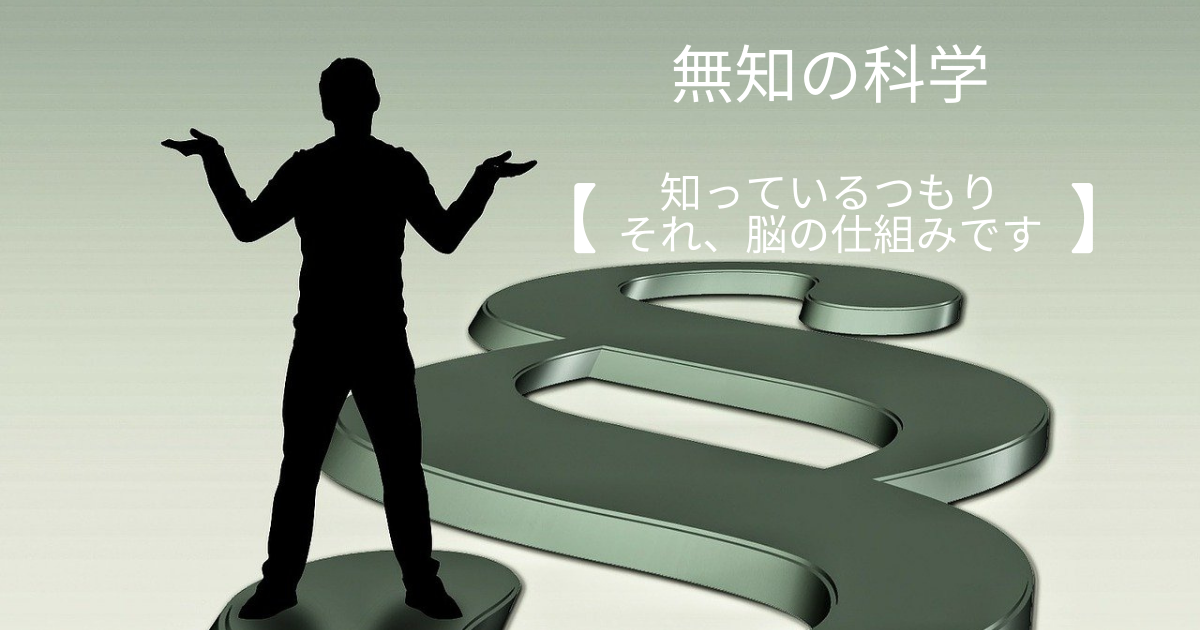
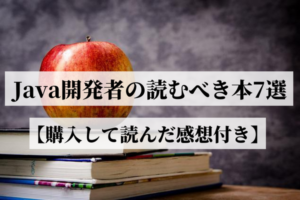
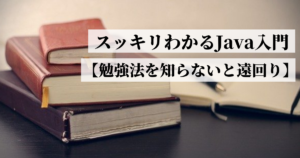
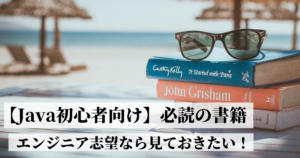
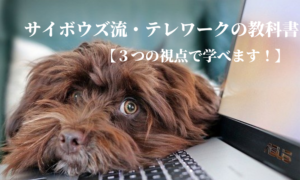




コメント